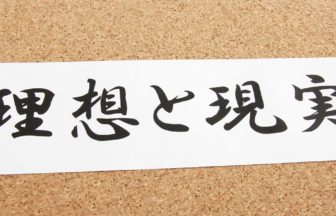煩悩(ぼんのう)とは心身にまといつき、心を乱し悩ませることです。仏教で多く出てくる煩悩ですが、心身を乱し悩ませる三毒(さんどく)があります。良くも悪くも現代では煩悩のバランスが大事かと思います。仏教では、煩悩を取り除くことを目指すための様々な修行や方法があります。
※仏教で必ず煩悩が取り除かれる保証はありません。
三毒とは
三毒とは貪・瞋・痴(とん・じん・ち / とん・しん・ち)と言われる3つの煩悩のことです。
貪 → 貪欲(とんよく)
意味は非常に欲が深いことです。知識の吸収、体を鍛える、ビジネスを成功させるために働く、異性にモテたいために頑張るなどの貪欲は良い意味です。しかし、人はなぜか無限に貪欲してしまうことがあります。いきすぎた貪欲により心身を乱し悩ませることになります。
瞋 → 瞋恚(しんに)
意味は怒り、憎しみ、嫌うことです。怒りや憎しみの炎を建設的に良い原動力へと変えることが出来れば良いのですが、いきすぎた瞋恚は心身を乱し悩ませることになります。
痴 → 愚痴(ぐち)
意味は愚か(おろか)なことを言うことです。愚痴を言ってスッキリする気持ち分かります。ストレスの多い現代では、大事かもしれません。しかし、いきすぎた愚痴も心身を乱し悩ませることになります。愚痴が多い状態から抜け出すために、まずは心身を良い状態に向け行動する必要があります。

人間には108つの煩悩があると言われています。除夜の鐘を108回つくのはこの煩悩を退治するためです。しかし鐘をついても、煩悩がなくなることはありません。今回記事にした三毒をよく知り、上手く生きていくことで心身を乱さないような生活が出来ます。煩悩をなくすことは難しいですが、それをコントロールすることが大事です。